備蓄米放出でも価格が下がらない
お米がまだまだ足りていないのか?
2025年4月に備蓄米が放出されてもコメの価格は未だ上がり続けて、スーパーに行っても、まだまだ品切れ状態が多い。
備蓄米放出が叫ばれ農林水産省も重い腰を上げたが、それでも解決されない。
農水省の江藤大臣は、「米を買ったことがない」とリップサービス?で発言して大炎上中🔥w
農林水産省のおそまつ対応は、こちらの記事で解説中 ↓
「米が足りない!」私がクソつまらん公務員を退職したワケ 番外編【2024年の米不足に対応できない三流官庁】

なぜ価格が下がらない??
世間やマスコミでは、コメの価格が下がらない原因が多方面から分析されている。
その根底には戦後から続く日本独特な米の流通システムがあるほか、さまざまな要因が関わっているのだろう。
この記事はその要因を分析するとともに、今後の見通しについても推測する。
最後までお読みいただくと、今後のいち消費者としての心構えなどを得てもらえるはずだ。
公務員を退職した私のこと(プロフィール)
田舎の県で地方公務員として、約15年間勤務する。
前職の経歴と風貌から、税金の徴収係などハードな部署に回され続ける。
勤務10年目で第二子誕生の際、当時の男性では珍しい1年間の育休を取得。
育児をこなしながらも今後の人生を真剣に考え、公務員を退職して独立。
公務員時代の最終年度は、「有給消化46日/年度」という伝説的記録を叩き出す。
「あれだけ休んで、業務ノルマを軽く達成したイクメン」として同僚から注目を集めるが、上司からは「休みすぎ」という理由で最後に減点評価をされる。
小規模農業、ブログ運営、海外輸出を展開中。
もっと細かく知りたい方 → 私のプロフィールへ(内部リンク)

米の価格が下がらない原因
米の価格が下がらない原因として指摘されているものを、列挙してみる。
1. 備蓄米の性質と用途の制限
政府が保有する備蓄米は、「特別用途米」として、主に以下のような目的で備蓄されている。
- 災害時の非常食
- 食糧不足時の供給調整
- 学校給食や業務用への供給
- 海外援助など
これらは基本的に「古米(こまい)」であり、収穫から数年経っているものも多く、風味や食感において新米とは大きく異なる。
そのため、一般消費者向けのスーパーなどの「家庭用市場」にそのまま流通するケースは少なく、用途が限定される。
ブレンド米という形で流入してくるだろうが、備蓄米がどれだけの割合になるのかは業者のみが知っている。
備蓄米は「公的売渡」として業者に売却される仕組みで、市場価格ではなく条件付きで取引(入札)されるため、民間流通の価格形成に即効性を持つとは言えない。
遅れてでも効いてくればよいのだが💦

2. 流通構造の問題:全農の影響力
日本の米流通は、他の食料品に比べて非常に独特な形だ。
特に重要なのが、「全農(全国農業協同組合連合会)」の存在です。
全農は全国の農協(JA)を束ねる組織であり、日本国内の米の流通のかなり大きな割合を担っている。
今回の備蓄米を落札した9割以上は、この全農だ。
農家が収穫した米は地域のJAに出荷され、全農を通じて卸売業者や小売業者に流れていく。
この中央集権的な仕組みによって、流通の安定性はあるものの以下のような弊害も生じる。
- 価格の硬直性:全農が価格決定において強い影響力を持ち、需給の変化に即応しにくい。
- 在庫の調整力:全農が大量に米を保有している場合、価格下落を防ぐために放出を遅らせる、あるいは制限する可能性もある。
- 市場の透明性の低下:米の取引が実質的に閉鎖的なネットワーク内で完結しているため、市場原理が働きにくい。
つまり備蓄米が政府から放出されても全農がそれを吸収し在庫として保持することで、一般の小売価格には影響が及ばない構造が強く指摘されている。
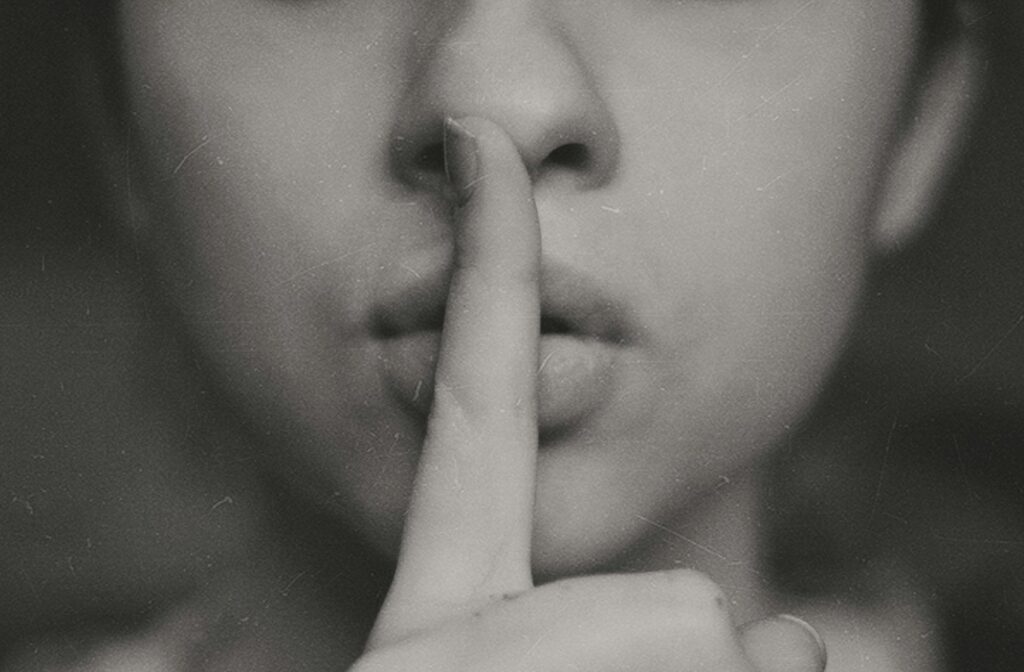
農家を守りたい農協
いままで米農家は安いお米の卸売り価格にとても苦しんでいた。
もし現在の店頭価格が生産農家にしっかり反映されているのならば、農家保護という観点からは良いのかもしれない。
もしそれがJAや全農を肥大化させるためだけに用いられていれば、しかと糾弾しなければならない。
そういう意味で2024年度の全農などの決算報告をとても心待ちにしている。
3. 卸売と小売の間にある“壁”
備蓄米やその他の米が市場に出たとしても、それが消費者の手元に届くまでには、いくつもの流通業者を経由する。
主なものは、以下の流れだ。
農家 → JA(農協)→ 全農 → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者
この過程で、各段階にマージン(利益)が乗せられ、また、販売戦略や在庫調整の影響で価格が操作されることもある。
たとえば、小売業者が高値で仕入れた米がまだ在庫にある場合、仕入れ価格より安く売って損をするわけにはいかないため、しばらくは価格を下げないという判断がされることもある。
最近では人件費やエネルギーコストの高騰が進んでおり、仕入れ価格が下がっても小売価格に反映されないケースが多くなっている。

4. 消費者の“こだわり”とブランド志向
お米は単なる主食というだけでなく、消費者の「味へのこだわり」や「ブランド志向」が強く出やすい食品だ。
例えば、コシヒカリやあきたこまち、ゆめぴりかなど特定の品種に人気が集中している。
備蓄米の多くはブランド米ではなくブレンドや古米、業務用であるため、たとえ価格が下がったとしても消費者の選好とは一致せず、販売に苦戦することも考えられる。
このため安価な備蓄米が市場に出ても、「消費者の購買行動を動かす力」が弱く、結果として店頭価格が変わらないという現象も想定しうる。
5. 輸入米との関係や国際事情
日本は一部のお米をWTO(世界貿易機関)ルールに従って輸入している。
これらのお米はミニマム・アクセス米と呼ばれ、多くは業務用や加工用に回されており、店頭価格には直接影響しない構造だ。
一方で、世界的な穀物価格の上昇や為替の円安が続くと輸入コストも上がり、国内米に対する相対的な価格低下圧力が弱まる傾向も指摘されている。

過去の備蓄米
備蓄米は過去にも放出されたことがあったが、当時はどのような変化があったのだろうか?
◆ 1993年の“平成の米騒動”(冷害による米不足)
1993年は記録的な冷夏で、全国的にお米の大凶作となった。
特に東北地方での被害が深刻で、生産量が前年比74%まで落ち込むという非常事態に至った。
そのため全国で品薄となり価格が急騰した結果、スーパーからコメが消え「平成の米騒動」と呼ばれた。
このとき政府は以下のような緊急措置を講じた。
- 備蓄米の放出(放出量:約40万トン)
- タイなどからの緊急輸入(ミニマム・アクセス外の臨時輸入)
これらの施策によって一時的に市場が落ち着き、価格の暴騰は抑えられたことにより、備蓄米の放出は一定の効果を発揮し「緊急時には備蓄米が価格安定に役立つ」という前例となった。
ただし輸入米(インディカ米)には強い風味やパサパサ感があり消費者に受け入れられず、むしろ「日本の米のありがたみ」が再認識されたという副次的な効果もあったようだ。
◆ 2008年~2010年の世界的な穀物高騰期
この時期、世界的な食料価格が高騰し、米や小麦、トウモロコシの価格が跳ね上がった。
原因は、原油高、気候変動による不作、新興国の食料需要増、バイオ燃料需要などが挙げられる。
日本ではこの影響を受け業務用米や加工用米の価格が上昇し、飲食店や食品メーカーはコスト圧力に苦しむこととなった。
そこで政府は次のような対策を講じた。
- 加工用・業務用向けの備蓄米の放出
- 国産米の業務転用の奨励(飼料米や加工米への切り替え支援)
これにより一部の業務用市場では、価格の上昇が抑えられたとされている。
しかし店頭価格への影響は限定的で、家庭用の価格を直接下げるほどの影響力は持たなかったとも分析されている。
まとめ:構造の問題が価格の硬直性を生む
政府が備蓄米を放出しても店頭価格が下がらない理由は、単に量が足りないからではない。
その背景には、先ほど挙げた構造的な問題もある。
- 備蓄米の用途が限定されている
- 全農など大手流通の価格調整機能
- 複雑な流通経路と在庫調整の壁
- 消費者のブランド志向と古米への抵抗
- 国際的な物価高の影響と相対価格の変動
つまり、「備蓄米が出ればすぐ価格が下がる」という単純な話ではなく、制度、商慣習、消費者心理、そして業界の力関係が複雑に絡み合っているのだ。

今後、どうなるのか?
第1回の備蓄米の放出ではお米の価格は下がらなかったことを受け、農水省は2025年の夏までに入札を連続開催することを決定した。
ただそれでも価格が下がるかどうかは、神のみぞ知るところ。
もはや国の管理で価格を安定的に保つことは、不可能ではないか?
全農や買い占め業者の悪行があればしっかり糾弾されるべきだが、もはや消費者としては「お米はこの価格になってしまった」という認識が必要なのかもしれない。
状況によっては、海外米が日本の食卓に並ぶことさえ当たり前になることも考えられる。
そうなることも念頭に置きつつ家計管理を見直し、しっかり対応できる国民ではありたい。
しばらくはこの価格が続くようであれば、減反によって離米していた米農家は再び米作りを始めるだろう。
そして農地集約により大手の農業法人が誕生すれば、全農の意のままに米価を操ることも困難になるはずだ。
この数年は、米の生産を根本から立て直す我慢の時と考えて耐えるべきなのかもしれない。
最後に改めて強調するが、買い占めや保留で価格を吊り上げている輩は心から軽蔑する。
あわせて読みたい おススメ記事
・大学授業料の前に、こどもたちの給食が大ピンチ!
『 【給食会社が大ピンチ!】子どもを脅かす給食停止問題の原因 』

・やっぱりあった、教育委員会のなれ合い人事。悪習誕生のメカニズムとは?
『 【賄賂?裏金?まだやってるの】名古屋市の教員団体が教育委員会に金品上納 』
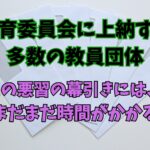
・セコ公務員の哀れな末路! 子どもに教えたい持続するサービスとは?(内部リンクへ)
『 【懲戒処分がラージ級!】コンビニ コーヒー注ぎすぎ校長にみる「誰もが誘惑されてしまう心理」と予防策 』
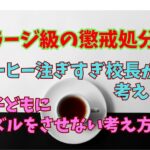


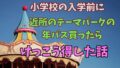
コメント