「こども誰でも通園制度」とは
国が大見得を切って導入を発表した「こども誰でも通園制度(仮称)」。
これは就労していない親でも月に一定時間、子どもを預けられるようになる新たな通園制度。
親の就労を原則とする現行の保育所制度を拡充する形で、対象となるのは0歳6か月から3歳未満の幼児だ。
国は、2023年9月から導入に関する検討会を開始した。
同年12月には第4回の検討会を開催し、中間案のとりまとめまで完了している。
2023年度内におよそ150の自治体でモデル事業を導入し、2025年度に新制度スタートの予定。
2026年度から全国の自治体で利用できるようにする方針が盛り込まれた。

創設の名目は、未就園児を育てる親の孤立を防ぐとともに、ほかの園児との触れ合いを通じて子どもの成長を促すこと。
病児保育などの福祉の観点からではなく、あくまでもすべてのこどもの生育環境整備とのこと。
私は腑に落ちないところがあるのだが、読者のみなさんはお気づきだろうか?
・本当につまらない検討資料ですが、こども家庭庁のリンクを貼ります ↓
新制度に、若干の期待
この「こども誰でも通園制度」は、親の就労条件を問わずに子どもを預かってもらえる新制度。
現行の制度では、親が就労していないと原則として保育園で預かってもらうことができない。
たしかに保育園はそういうもので、一見納得できる理屈。
しかし実際の家庭では、まずは子どもをどこかで預かってもらえないと、就労のための就活さえできない。
核家族やシングルマザーならば、さおさらだ。
だからこそ、国は毎月一定枠の中で誰でも子どもを預けられる仕組みを創設するのだ。
この新制度が始まれば、助かる家庭は多いだろう。
しかし、どうしても引っかかるポイントが2点ある。
- 制度の名目が「すべての子どもの生育環境整備」
- 対象が「生後6か月~3歳未満」
子どもが3歳になったら、この制度は利用不可。
「それまでに保育園に正式入園しなさいよ~」という魂胆が透けてみえる。
そして正式入園するということは、親の就労が基本。
よって、この制度は「誰でも通園可能」と謳いつつ、期限を区切って親の就労を促す目的なのだ。

「親の就労を促す」ことは、問題と感じない。
おかしいのはそれをひた隠しにして、あくまで「子どもの生育環境整備」を謳うこと。
本当に「誰でも通園」させたいなら、対象を「未就学児」にすればよいだけだ。
今回の記事では、大風呂敷を広げたように見えてせこい仕組みにしている国や政府の思惑を、予算担当公務員の視点から読み取っていく。
制度も生煮え状態、これから予算制約の面で骨抜きが横行するだろう。
そんな政府の横暴を見逃さないために、保護者だけでなく幅広い層の国民に読んでもらいたい。
せこくておかしな制度だけ創設しても、この国の保育・教育環境は改善しない。
わが家&私のこと
田舎の県で地方公務員として、約15年間勤務する。
地方自治体ながら、予算編成の最前線にて数年間こき使われた。
その際、予算の面から、国や自治体が手掛けるセコい政策形成の手法を学ぶ。
勤務10年目で第二子誕生の際、当時の男性では珍しい1年間の育休を取得。
育児をこなしながらも、「このままでは人生にきっと後悔する」と思い至る。
今後の人生を真剣に考えた結果、公務員を退職して独立。
引き継いだ農地で小規模農業を行いつつ、ブロガーとして歩み始める。

・もっと細かく知りたい方 → 私のプロフィールへ(内部リンク)
・こども家庭庁の公式ホームページについては、外部リンクへ ↓
またやってる「仮称」(嗤)
今回の「こども誰でも通園制度」、そこにしっかり付いてた(仮称)。
このような新制度が創設されると、もれなく付いてる(仮称)。
いつからか分からないが、公務員の世界で超流行している便利ワードだ。
「名称がダサい、センスない」と言われても、「仮称の段階ですから」と逃げられるのだ。
時期が来れば、知らない間に(仮称)はなくなっているだろう。
おそらく中央官僚が発明したものだが、地方自治体でも確実に流行している手法だ。
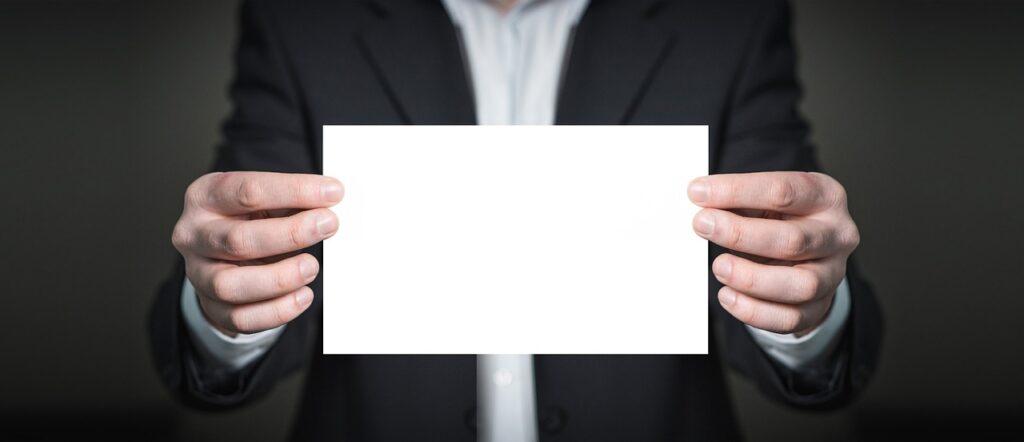
特に弊害はない
鋭い読者さんは「仮称ならば、正式名称がガラッと変わり中身も骨抜きされるのでは?」と、不安になるかもしれない。
しかしそれは全くの杞憂である。
結論として、そんな危ない橋を渡る官僚はいないし、そんな胆力のある政治家もいない。
仮称から名称が変わったとしても、首相や大臣が思いつきで再ネーミングするくらいだ。
ここで大事なのは、検討段階でしっかり国民の目を光らせておくこと。
そもそも「誰でも通園制度」と言いつつ対象期間が限られていることから、骨抜きが進行している。
名称よりも、まさに今が大事なのだ。

本当の狙いを隠した意図
冒頭で触れたように、今回の「誰でも通園制度」の真の狙いは、親の就労を促すこと。
ただ露骨にそれを打ち出しても、ナイーブな国民が不満を訴え支持率が下がる。
それを恐れた政府は、「子どもの育児環境の整備」と子どもを完全な「ダシ」に仕立てた。
ここまで魂胆が見え見えの施策を打ち出すのか。
こういうことを国会の答弁で言える厚顔無恥さが、国会議員や官僚による答弁の才覚なのだ。
就労しない道
保育園制度の条件として「就労」ばかり語っていたが、実は違う方法もある。
子どもを保育園に預けるには、親が個人事業主として「開業」するという手もある。
田舎では、家族で営む「農業」も立派な個人事業だ。
都会のアパートの一室でも、「開業」することはできる。
コロナ禍による働き方の変化を受けて、国民のワークスタイルも確実に変化しているのだ。
そしてなによりも、個人事業主はいわば雇い主&就労者。
当然ながら自ら稼ぐという責任が伴うが、就労時間も自由に決定でき、保育園に「就労証明書」も提出できる。
煩わしそうな開業届は、無料の税務ソフトなどからダウンロード可能。
プリントアウトして、所管の税務署に提出すればOK。
1週間ほどすると、受付印が押印されたコピーが返ってくる。

検討会のメンツ
検討会のメンツを確認すると、大学教授、育児関連団体のほかに、福岡市などの自治体が目立つ。
ほかにも栃木市、大阪府高槻市、千葉県松戸市の各役職者が名を連ねる。
これらは、すでに2023年度に「モデル事業」としてこの制度を先行導入している自治体だ。
テスト的に導入された自治体の「生の声」を反映させる狙いだ。
参加する自治体としても先進性をアピールでき、こども家庭庁を助けて貸しを作れるメリットがある。
誰でも通園制度の心配事
今回の新設制度とよく対比されるのは、2006年に開始された「認定こども園」制度。
認定こども園とは、教育・保育の一体的に行ない、幼稚園と保育所の双方のメリットを併せ持つ施設。
認定基準を満たせば都道府県等から認定を受けて開始することができる。
その際はけっこう話題になったのだが、「それによってどう変わったか」がまったく伝わってこない。
結局、誰がどう評価するのだろうか。
しかし、今回の「こども誰でも通園制度」は、全国一律導入を目指すもの。
もちろん全国の自治体間で、必要度の濃淡の違いがある。
そのため自治体の力の入れ具合も、まちまちになるだろう。

ただ政府も本気度を示すため、導入を促す補助金も公表されている。
こども家庭庁→自治体→保育施設という流れだろうか。
そして、総務省による普通交付税にも加算されるだろう。
政府はいろいろな「ニンジン」をぶら下げて、制度のスムーズな導入を図るのだ。
大変なのは、各自自治体の担当者。
制度準備が遅いと、「なんでうちの自治体は何も発表されないの」とお叱りをうけることにになる。
きっと市長や村長からお尻を叩かれて、せわしない1年になるだろう。
ごくろーさまです。
まとめ こども誰でも通園制度でも、またやりおった
今回の「こども誰でも通園制度」は実現すれば、助かる人もいるだろう。
ただそれでも中身をよく確認すると、またもや「限定」だらけ。
政府のこのやり方は、もうみえみえだ。
先の「3人いたら大学無償化」と同じように、大きそうな風呂敷に見えても実態はショボい。
そして財源不足の日本では制度が新設されて予算拡充されると、どこか知らないところが削減されている。
子どもの大事な未来を護る保護者として、「何かが増えた分、何かが減らされている」という感覚で、これからも政府発表を疑い、監視の目を光らせる必要がある。

あわせて読みたいおススメ記事
・「異次元の少子化対策」で注目のこども家庭庁、くわしく解説中! 内部リンクへ ↓

『 【実はこの方は、、、】子ども家庭庁の加藤新大臣は、どんなひと? 』

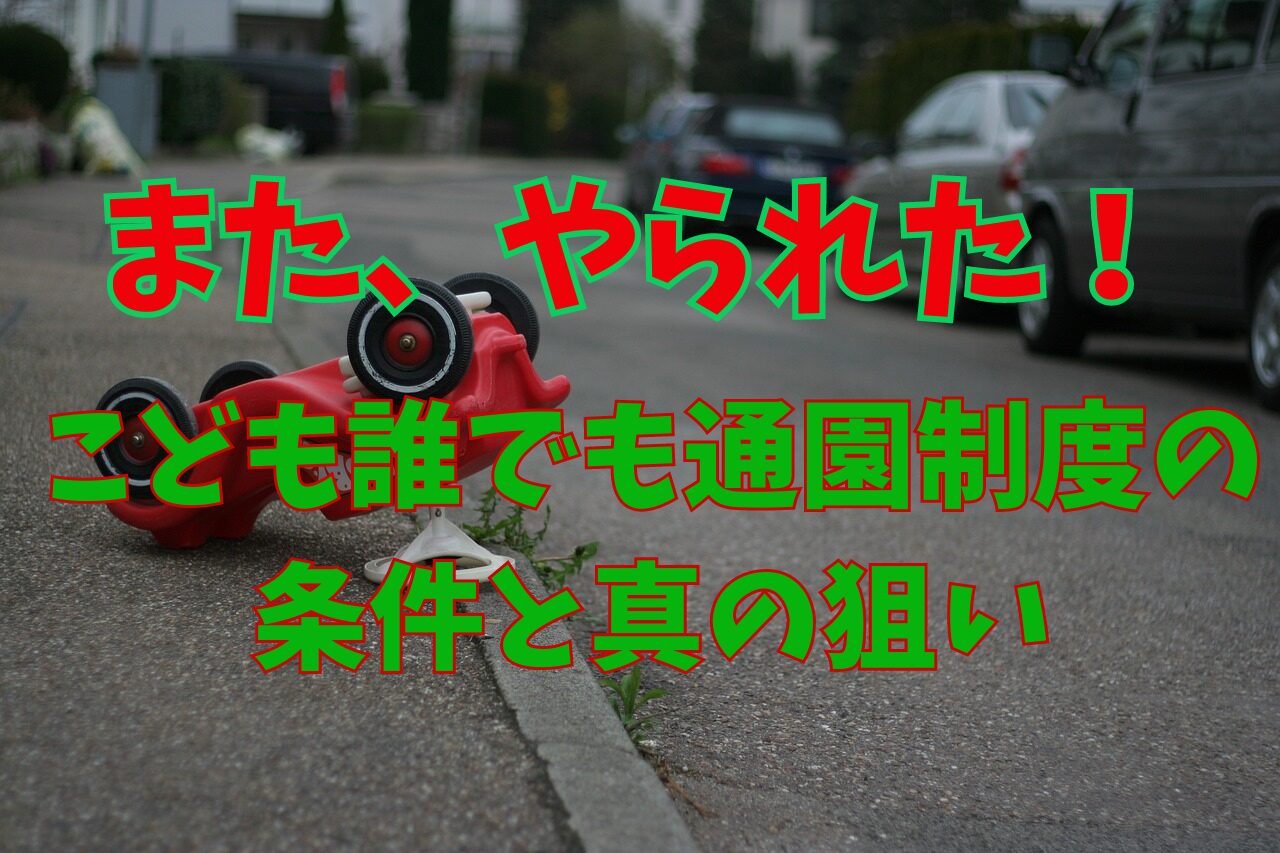


コメント